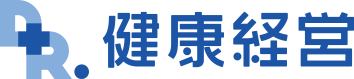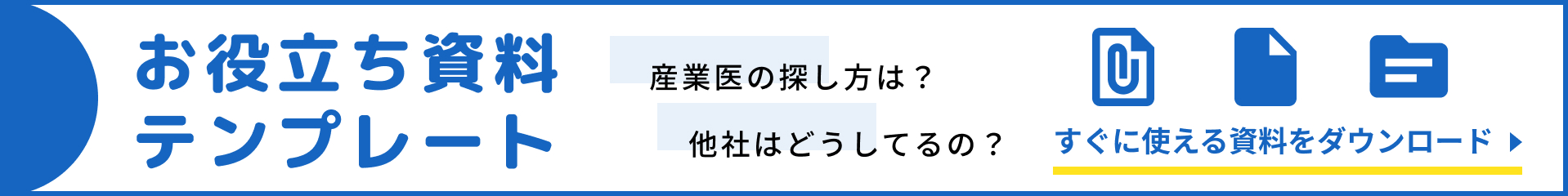メンタルヘルス・ストレスチェック
ストレスチェック集団分析とは?評価方法や具体的な活用方法を解説

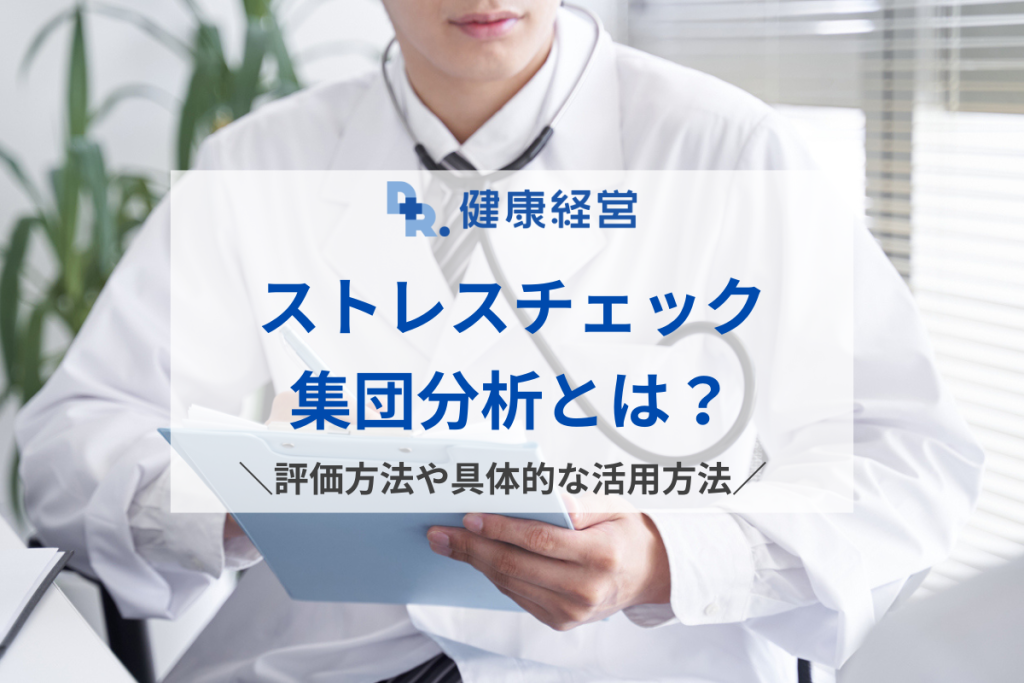
ストレスチェックの実施後に集団分析することで、職場全体としてのストレスの程度や傾向を把握でき、職場環境の改善に活かせます。
しかし、集団分析とはどのようなもので、実際に得られた分析データをどう判断すればいいかわからない方も多いでしょう。
本記事では、ストレスチェックの集団分析の概要やメリット、実際の判断方法などを紹介します。集団分析のデータを最大限活かして、自社のストレス対策を成功に導きましょう。
目次
ストレスチェックの集団分析とは?

ストレスチェックの集団分析とは、労働安全衛生法で義務付けられた「ストレスチェック」で得られたデータを、事業場やグループなどの集団単位で集計・分析を行うことです。ここでは、ストレスチェックの集団分析の目的やメリットなどを解説します。
ストレスチェックの概要については『ストレスチェック制度の目的とは?義務となる企業や対象者は?』を参考にしてください。
集団分析の定義
集団分析とは、ストレスチェックの結果を集団(部署など)ごとに集計して分析・解釈することです。厚生労働省の「ストレスチェック制度実施マニュアル」に基づいて、集団分析の結果を評価します。
編集作業をする際は、厚生労働省が提供する「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」をダウンロードして使用すると便利です。
企業にとってストレスチェックの集団分析は「義務」ではなく「努力義務」という扱いになります。しかし、実施すると多くのメリットを得られるため、積極的に評価することをおすすめします。
※出典:厚生労働省「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」
集団分析の目的とメリット
集団分析を行うと、職場環境に潜むストレス要因を明確化して改善につなげられます。個々の労働者から得た回答を集めるだけでは、企業環境の問題を把握できません。
集団分析をして事業場全体の傾向を見ることで、個人の偏りを除いた職場の問題点を自覚できるでしょう。さらに、部署単位での集団分析の結果を比較すると、業務過重の多い部署や仕事コントロールの良好な部署などがわかります。
また、ストレスチェックの個人結果は実施者(産業医など)から労働者へ提供されるため、労働者本人の同意がなければ企業側は閲覧できません。集団分析だと個人情報が明確にならないため、企業側でも閲覧可能となり現在の職場環境を把握できます。
ストレスチェックの集団分析を行う際の3ステップ
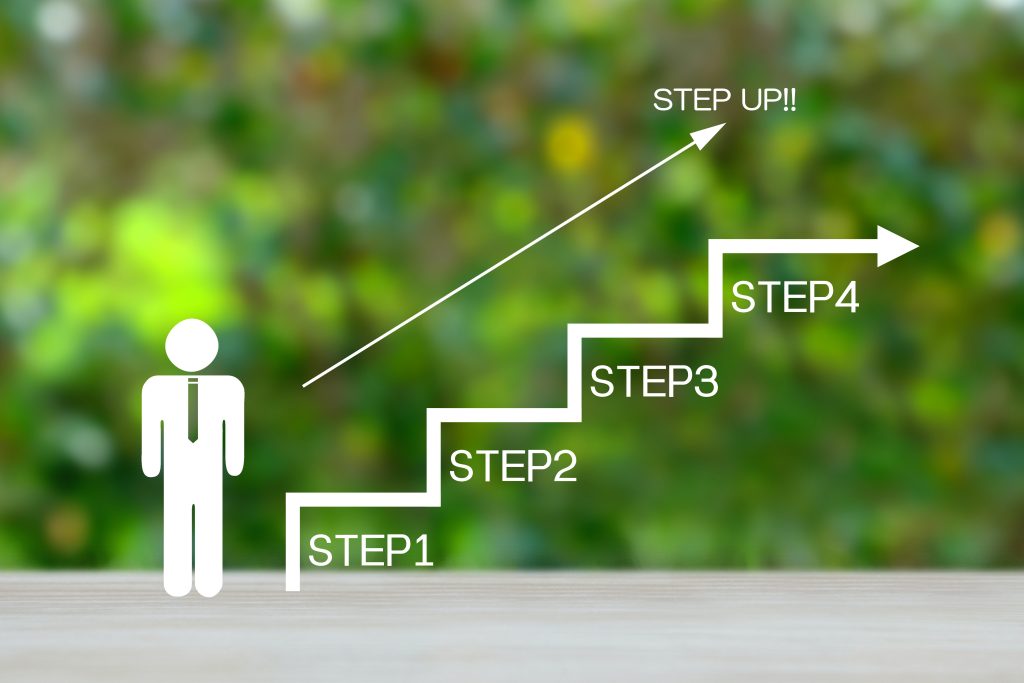
ストレスチェックを行う際の3ステップは、以下のとおりです。
-
- ・ストレスチェックを実施できる体制を整える
- ・ストレスチェックを行う
- ・結果を集計して分析を行う
それぞれのステップについて詳しく解説します。
1.ストレスチェックを実施できる体制を整える
まず、ストレスチェックを実施できる体制を整えましょう。事業者は、ストレスチェックを実施するにあたり、実施者を選ばなければいけません。実施者は、以下に該当する人物の中から選定されます。
-
- ・医師
- ・保健師
- ・看護師
- ・精神保健福祉士
- ・歯科医師
- ・公認心理士
ただし、医師や保健師以外が実施者となる場合は、厚生労働省が定める研修を終了しておく必要があります。実施者は有資格者であれば対応可能であるものの、事業場の状態を日頃から把握している産業医がもっとも望ましいでしょう。
そして事業者は、実施者の指示に基づいて補助業務をする実施事務従事者も併せて選定します。実施事務従事者には、産業保健スタッフや事務職員などが指名されるのが一般的です。
なお、実施事務従事者はストレスチェックの結果を閲覧できるため、人事に関する権限がある人を従事させることはできません。従業員に不利益が発生しないように注意しながら人選を行ってください。
2.ストレスチェックを行う
ストレスチェックを実施できる体制が整ったら、実際にストレスチェックを行ってみましょう。従業員全員にペーパー、もしくはオンライン上でストレスチェックに回答してもらいます。ストレスチェックの質問票に指定はないものの、以下に関する質問を含めておかなければいけません。
-
- ・ストレスの原因に関する質問項目
- ・ストレスによる心身の自覚症状に関する質問項目
- ・労働者に対する周囲のサポートに関する質問項目
もし、質問の決め方に迷うようであれば、厚生労働省が推奨する「職業性ストレス簡易調査票」をご利用ください。
※参照:厚生労働省:ストレスチェック制度簡単!導入マニュアル
3.結果を集計して分析を行う
従業員全員のストレスチェックが終了したら、実施者がそれぞれの回答を集計して評価判定を行います。従業員1人ひとりの評価判定が終了したら、その結果を集団ごとに分けて分析します。
なお、ストレスチェックの評価判定や分析は事業者内で実施できるものの、負担を減らしたいときは外部委託することも可能です。
ストレスチェック集団分析の評価方法
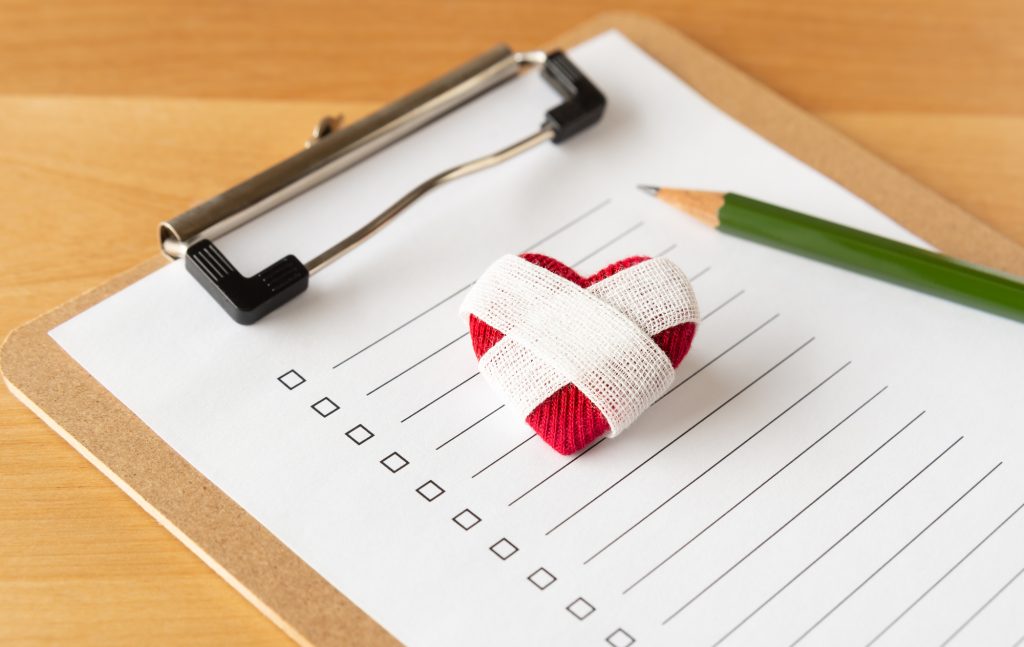
厚生労働省はストレスチェックの集団分析を行う際に「仕事のストレス判定図」を使用するよう推奨しています。本省では、仕事のストレス判定図の詳細を解説します。
仕事のストレス判定図を使用する
仕事のストレス判定図は「量-コントロール判定図」と「職場の支援判定図」の2種類があります。これらの判定図を使用すると集団におけるストレスの度合いや、健康リスクへの危険度を判定できます。まずは、2つの判定図の詳細をチェックしましょう。
量-コントロール判定図
量-コントロール判定図とは「仕事の量的負荷」と「仕事のコントロール(裁量権)」を軸としてストレスを判定するためのものです。自社の集団から得たストレス度のプロット(黒い点)を全国平均と比べられます。判定図の右下にいくほど高ストレス、左上にいくほど低ストレスであると判断できます。
職場の支援判定図
職場の支援判定図とは「上司の支援」と「同僚の支援」を軸にストレス判定を行うものです。量-コントロール判定図と同様に、自社の集団のプロットと全国平均を比較できます。左下に近づくほど高ストレス、右上にいくほど低ストレスを判定されます。
総合健康リスクを評価する
仕事のストレス判定図が完成したら、総合健康リスクを評価しましょう。総合健康リスクとは、職場環境が従業員の健康にどの程度影響があるのかを示したものです。数値が高いほど高リスクと判断されるため、職場環境の見直しを行う必要があります。
仕事のストレス判定図を点数化したものが「健康リスク」であり、健康リスクはさらに「健康リスクA」「健康リスクB」「総合健康リスク」に細分化されます。
健康リスクAは、量-コントロール判定図から得られる数値であり、全国平均を基準(100)として自社集団のストレス度を見るものです。健康リスクBは、職場の支援判定図から得られ、健康リスクAと同様に全国平均(100)が基準になっています。
総合健康リスクは「健康リスクA」×「健康リスクB」÷100で算出する数値です。例えば健康リスクA=100、健康リスクB=120のときの総合健康リスクは以下のように算出します。
-
- 総合健康リスク:100×120÷100=132
この数値は、従業員の健康への悪影響が平均よりも32%高いことを示しています。総合健康リスクが150を超える場合には健康問題が発生している例が多く、120を超えているケースでは問題が顕在化する前に対策を始める必要があるとされています。
ストレスチェックの集団分析を活用した対策方法

ストレスチェックの集団分析を活用した対策は、以下の流れで実施しましょう。
1.まず、判定図での結果を元に「仕事量の割に自由度が少ない」など、職場のストレス問題の特徴を検討しましょう。その際、これらの項目はあくまでもストレスチェックを行った従業員の主観合計であることを念頭に置いてください。
2.次に、実際の職場において、それが具体的にどのような問題として生じているのかを実地調査しましょう。実地調査の方法は、産業医や衛生管理者の職場巡視、該当職場の上司、従業員からのヒアリングなどがあります。
3.集めた情報を元に、可能性のあるストレス要因として、できるだけ具体的な内容をリストアップします。例えば「生産ラインの作業スピードが早く、作業員が短時間でもラインを離れられない」などです。ストレス要因は、下記のように分けて整理するとよいでしょう。
-
- ・仕事の量や複雑さの問題
- ・仕事の自由度や裁量権の問題
- ・職場の人間関係やサポートシステムの問題
4.リストアップされたストレス要因に対して、それぞれ該当職場の上司や産業医、衛生管理者、人事労務担当者などで話し合い、実現可能な改善計画を立てます。効果的な対策になるよう、従業員も参加できるように配慮するとよいでしょう。
5.対策を立てた後は「計画通りに実行されているか」「実施上の問題は起きていないか」など、進捗状況を定期的に確認します。
6.対策後はその効果を評価しましょう。なお、医療費や疾病休業などに対する効果は、半年から数年の観察期間が必要です。
集団分析を活用した具体例3選
ストレスチェックの集団分析を活用した具体例を3つ紹介します。
-
- ・「仕事の量的負担」が多い場合
- ・「仕事の量的負担」と比較して「仕事のコントロール」が低い場合
- ・「上司の支援」「同僚の支援」が低い場合
それぞれの具体例を詳しく見ていきましょう。
「仕事の量的負担」が多い場合
「仕事の量的負担」への対策は、生産性に結びついていない余分な作業を減らすことです。例えば、運転前後の機械チェックポイント数を軽減するなどの工夫があります。
また、仕事の進め方に問題があると「仕事の量的負担」が増加するため、作業が滞りやすくなります。作業を円滑に進めるためには、どのような対策が必要かを考えて具体的に改善していきましょう。逆に、仕事量が多いはずなのに「仕事の量的負担」の値が低めであった場合は、スムーズに仕事が進む環境が整っているといえます。
実質的な労働時間が1日10時間未満(週50時間相当、月残業時間50~60時間相当)になるよう計画を立て、効率のよい作業方法を工夫しましょう。
「仕事の量的負担」と比較して「仕事のコントロール」が低い場合
「仕事の量的負担」を比較して「仕事のコントロール」が低い場合は「仕事のコントロール」を増やしていきましょう。
自由度や裁量権など「仕事のコントロール」を増やすということは、個々の能力を発揮できる機会を作ることです。仕事の量的負担や職場環境、仕事の進め方に対して、従業員または作業グループ自らが問題を検討し、改善していけるような工夫が必要です。
仕事の目標や作業の見通し、作業の位置づけなどを職場のメンバー間で共有することで「仕事のコントロール」は改善します。OTJ(※)や技能研修の機会を作ることも「仕事コントロール」を増やすことにつながります。
※OTJ:on-the-job trainingの略。職場にいる従業員を職務遂行の過程で訓練すること。
「上司の支援」「同僚の支援」が低い場合
上司が多忙なゆえ報告や調整がしづらくなり「上司の支援」が低下するケースがよく見られます。また、トラブルが多い職場では「上司の支援」の必要性が増え、相対的に「上司の支援」が低くなります。できるだけ従業員が支援を必要としたときは、すぐに相談できる環境を作りましょう。
職場グループ内で情報共有の機会を増やすことも、上司や同僚の支援につながります。また、サブリーダーを置くなどして上司の代わりとなる人材を増やすことも一つの対策です。
また、職場が分散しているなど、社内のレイアウトによって上司や同僚の支援を低下させている場合があります。コミュニケーションがフラットかつ、円滑に進められるよう職場のレイアウトなどを工夫しましょう。
さらに、不公平感は職場の人間関係の悪化を招き、職場の支援を低下させる原因になります。上司から部下へ説明を行うときは誤解を生まないように配慮したり、オープンで公平な態度を取ったりするなど不公平感が生じないように気をつけましょう。管理監督者への教育や研修を通じて「上司の支援」を改善させることも可能です。
ストレスチェックの集団分析を行う上での注意点とポイント

ストレスチェックの集団分析を行ううえでの注意点やポイントは、以下のとおりです。
-
- ・集団規模は10人以上で行う
- ・分析結果は5年間保管する
- ・従業員全員が受ける
それぞれの注意点やポイントを詳しく解説します。
集団規模は10人以上で行う
ストレスチェックの集団分析は、基本的に10人以上の集団規模で行わなければいけません。なぜなら、10人以上の単位であれば個人を特定できないため、労働者の同意がなくてもストレスチェック実施者から事業者へと集団分析の結果を提供できるからです。
ストレスチェック受検者が10人未満となる場合には、原則として集計・分析結果の提供前に全員の同意が必要となります。「10人未満の部署しかない」などの理由で人数を確保できないときは、個人が特定されない方法を選択しましょう。
なお「集団規模が10人以上」というのは在籍する全職員の人数ではなく、ストレスチェックに回答した人の数である点に注意してください。集団とは業務内容や就労環境に共通点のある一定の部や課のことであり、集団の判断基準は事業者にゆだねられます。
分析結果は5年間保管する
ストレスチェックの結果は、5年間保存することが義務付けられています。また、実施者から提供された集団ごとの集計・分析結果についても、経年変化を見て職場のストレス状況を把握するなどの必要性から、事業者が5年間保存することが推奨されています。
なお、ストレスチェック結果記録の保存担当者は、実施事務従事者として規定された人になります。
従業員全員が受ける
集団分析を活用して職場環境を改善するためには、従業員全員の回答を集めることが必要です。なぜなら、一部の人の結果だけではデータに偏りが出てしまい、職場全体のストレス状況を把握できなくなってしまうためです。
ストレスチェックの実施は企業の義務ですが、労働者にとってはストレスチェックの受検は義務ではないため拒否される可能性もあります。職員全員の協力を得るためには、ストレスチェックの重要性を周知して理解してもらえるように働きかけましょう。
なお、集団分析で経年比較を行う場合には、条件や前提を一定にしておき、導入した改善策の内容や時期を一覧化しておくと成果を判断しやすくなります。
ストレスチェックを行うには産業医の選任がおすすめ
ストレスチェックを行う際は、産業医を実施者に選任するのがおすすめです。
労働安全衛生法第66条の10の定めにより、ストレスチェック実施者は医師、保健師その他の厚生労働省令で定める者から選ばなければいけません。
厚生労働省の見解によると「事業場の状況を日頃から把握している産業医などが実施者となることが望ましい」とされています。実施者を産業医にすることで、より職場環境を把握しやすくなるでしょう。
まとめ

ストレスチェックの集団分析は、職場のストレス状況を集団ごとに把握して環境の改善へとつなげるために有効な手段です。個々の回答を集計して得られる「職場のストレス判定図」を元に部署ごとのストレスを比較し、全国平均との差を確認しましょう。
株式会社Dr.健康経営ではストレスチェックの準備や実施、集団分析、高ストレス者のオンライン医師面談まで、手厚いサービスを提供しています。初めてストレスチェックを実施する企業にも安心の全面サポートをぜひご利用ください。
そのお悩み、Dr.健康経営に相談してみませんか?
「従業員数が初めて50名を超えるが、なにをしたらいいかわからない…」
「ストレスチェックを初めて実施するので不安…」
そんなお悩みを抱える労務担当者の方はいませんか?
Dr.健康経営では、産業医紹介サービスを中心にご状況に合わせた健康経営サポートを行っております。
些細なことでもぜひお気軽にご相談ください。